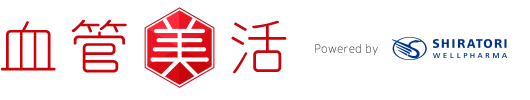機能性表示食品ってなに?
信頼して選ぶ、健康の新しいスタンダード
最近よく見かける「機能性表示食品」。
「目の疲労感を軽減する成分入り」「脂肪の吸収を抑える」などの表示がパッケージにあると、つい手に取ってしまいますよね。
でも、「普通のサプリと何が違うの?」「本当に安心?」という疑問も…。
実は、この「機能性表示食品」、私たちの毎日の健康をサポートするための食品として注目されています。
今回は、機能性表示食品とは何か、他の制度との違い、メリット・デメリット、そして信頼できる情報源まで、まるごとわかりやすくご紹介します。
機能性表示食品とは?

機能性表示食品とは、企業が科学的根拠に基づいて、特定の健康効果を表示できる食品のことです。例えば
•「内臓脂肪を減らすのを助ける」
•「お腹の調子を整える」
•「目のピント調節をサポートする」
など、体のはたらきをサポートする効果を商品のパッケージに表示できるのが特徴です。
平成27年4月にはじまった、この「機能性表示食品」制度により、私たちは商品の正しい情報を得て選択できるようになりました。
安心のしくみ ― 科学的根拠+届出制
この制度のポイントは、「企業が科学的なデータを基に、消費者庁に届出を行う」ということです。
国の審査(許可)はありませんが、届出の内容や根拠はすべて消費者庁のWebサイトで公開され、だれでも確認できます。
他の表示制度との違いは?
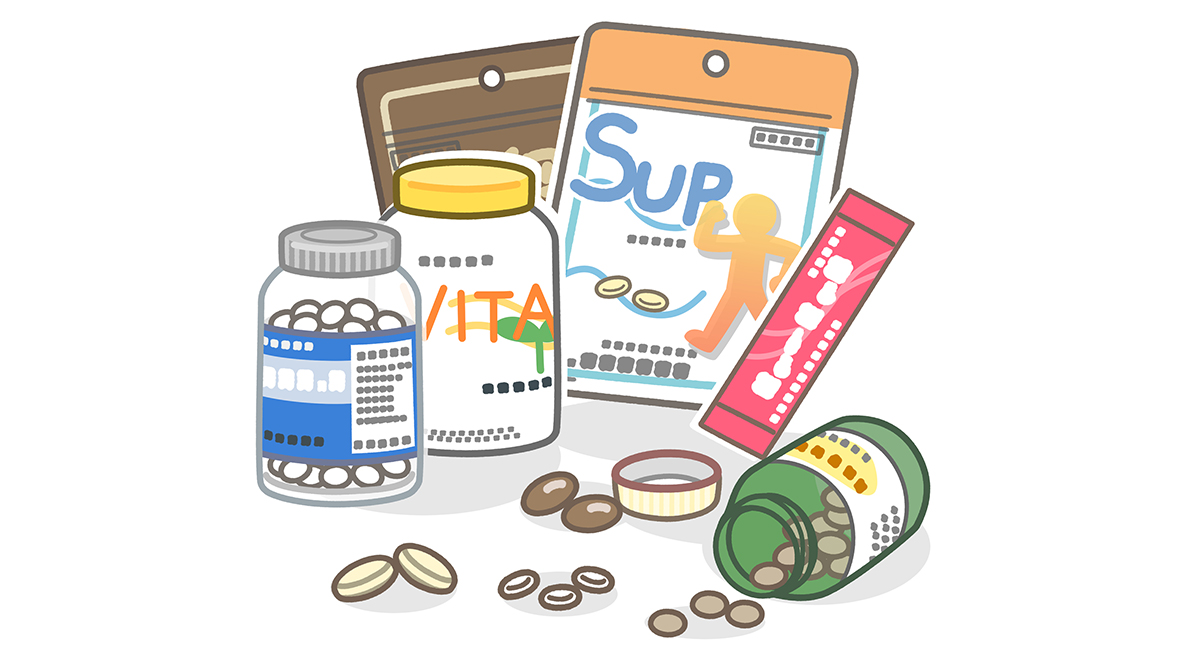
健康に関する表示ができる食品には、いくつかの制度があります。違いをまとめました。
1.一般食品
普通の食品。
「栄養豊富」などの表示はできますが、「疲労回復に効果」などの健康効果は表示できません。
特別な届出や根拠は不要です。
2. 栄養機能食品
国が定めた栄養成分(例:ビタミンやミネラル)について、「ビタミンCは皮膚の健康維持に役立つ」などの表示が可能です。
届出は不要ですが、表示できる成分・表現に制限あります。
3. 機能性表示食品
科学的根拠(論文や臨床試験)に基づいて、「内臓脂肪を減らすのを助ける」「睡眠の質を改善する」などの機能を表示できます。
企業が責任をもって国に届出を行います。
4. 特定保健用食品(トクホ)
「血圧が高めの方に」「お腹の調子を整える」などの表示ができる制度で、国が科学的根拠を審査・許可します。
厳格な基準をクリアする必要があり、その信頼性の高さが特徴です。
機能性表示食品のメリットとデメリット

メリット
•科学的根拠があるから安心
→ 信頼できる論文・データに基づいて表示されています。
•表示がわかりやすく、選びやすい
→ どんな健康サポートをするかが商品のパッケージに明記されているので、目的に合った商品を選べます。
•商品バリエーションが豊富
→ サプリだけでなく、飲料やスナック、青汁、ヨーグルトなど多彩な商品があります。
•生活に取り入れやすい
→ 医薬品ではないので、気軽に毎日の生活に取り入れられます。
•続けやすい価格帯の商品が多い
→ トクホと比べて審査コストがかからない分、手ごろな価格の商品が多い傾向があります。継続しやすさも健康管理には大きなメリットです。
デメリット(注意点)
•薬のように即効性はない
→ 続けて摂ることで体調のサポートになる、という“食品”としての位置づけです。
•個人差がある
→ 同じ商品でも、実感には差が出ることがあります。
•企業の自己責任制
→ 国が審査するトクホとは異なり、企業自身が科学的根拠の信頼性を担保する必要があります。
•表示に制限あり
→ 「高血圧を治す」など、医薬品的な表現は禁止されています。
自分に合った健康サポートを選ぼう

「機能性表示食品」は、信頼できる根拠のある情報を基に、自分の健康ニーズに合った食品を選べる新しいスタイルです。
薬ではないけれど、日々の健康管理に役立つ、そんな頼れる存在。
「体調が気になる」「いつまでも元気に過ごしたい」
そんな思いを持つすべての人へ。商品パッケージにある“機能性表示”をヒントに、あなたにぴったりの健康サポートを見つけてみてくださいね。
www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims